こんにちは保健師です!
こころの健康をキープするために(2020年5月)
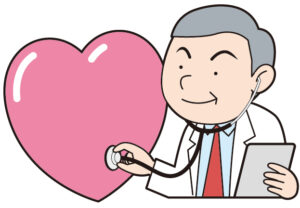
春は環境の変化や寒暖差による気温や気圧の変化が激しく、なんとなく気がのらない、だるさがとれない、元気が出ない等を感じることがあります。心と身体は密接に関係し、気持ちの切り替えやメンタルを強くするためには、身体の健康を保つことが大切です。
脳のメカニズムの一つである体内時計は、一日の活動に合わせて体温や血圧、ホルモン分泌などのリズムをつくっているため、体内時計がスムーズに働くと心地よさを感じられるように出来ています。体内時計を狂わせないためには、質の良い睡眠の確保とバランスの良い三度の食事が基本です。また、ストレッチやウォーキングなどの適度な運動をとりいれることは、血液の循環を良くするだけでなく、気持ちを晴れやかにする効果もあります。入浴はシャワーだけでなく湯船につかることもお勧めです。
読書や音楽鑑賞などの一人でも楽しめる趣味を持つことと、普段から人と接する、会話することで心の支えになります。直接会う機会がもてなくても、メールや電話でのやり取りをするだけで、気持ちが上向きになったり自分の考えがまとまったりして、心のモヤモヤがとれ、やる気が出たりしてきます。アロマなどの香り、波の音や小鳥のさえずりなどのヒーリング、植物や動物を育てる等で、おだやかな気持ちになれる方も多く、ご自身にあったリラックス法を知っておきましょう。
眠れない、食欲がないといった具体的な症状が続く場合は、かかりつけ医や心療内科を受診し、専門家に話す・内服するなど早めに手当てをすることも大切です。
首こり病(頚性神経筋症候群)(2020年4月)

頭は体重の約10%の重さがあり、例えば、体重60kgの人は6kgの頭を首が支えていることになります。携帯電話を使用している時などのうつむき姿勢は、頭の重さはこの2~3倍にもなり、首の筋肉が緊張し首こりを感じやすくなります。慢性的な緊張を強いられる筋肉は血行不良を起こし炎症状態へと移行していきます。
頚性神経筋症候群とは、首の筋肉の緊張と難治性の不定愁訴(原因不明の頭痛・めまい・疲労・多汗・不眠・胃腸症・血圧不安定など)を症状とする状態をいいます。首には副交感神経があり、副交感神経は内臓や血管・呼吸器などをコントロールする重要な神経の一つで、うまく働かなくなると自律神経に異常をきたすため、全身に様々な症状があらわれてきます。
日頃から前屈みにならないよう姿勢を正すことが基本です。首の筋肉をゆるめるには、15~30分に1回は首や肩をまわしてリラックスさせ、ホットタオルや入浴などで首を暖めることも効果的です。ビタミンEとビタミンCは血流を良くする働きがあるため、かぼちゃやブロッコリーなどの野菜や果物を意識して摂るよう心がけてください。筋肉や神経の動きをよくするカリウムやカルシウムは乳製品や緑黄色野菜に多く含まれています。質の良い十分な睡眠時間を確保することも大切です。
自覚症状がでてきた時には注意が必要です。早期に受診し重症化を防ぎましょう。首こりの他に、頭痛やめまい等がある場合は脳神経科を、腕や手のしびれがある場合は整形外科を、吐き気や脱力感・息苦しさなどがある場合は心療内科の受診が考えられます。消炎鎮痛薬・筋弛緩薬の他、ビタミン剤、湿布やローションなどの外用薬など、症状にあった薬を処方してもらい早めの対処をしてください。
ピロリ菌と胃潰瘍(2020年3月)

ヘリコバクターピロリ菌・通称ピロリ菌は、胃の表層を覆う粘膜に住みつく細菌です。胃液には強い酸性の塩酸が含まれているためほとんどの菌は生息できないのですが、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を出すことによってアルカリ性の物質を作り出し、塩酸が中和され胃が酸性ではなくなるために生息が可能となります。感染経路ははっきりとは分かっていませんが、水や食べ物と一緒に口に入ると考えられています。子どもの頃に井戸水などを使用していた方など、特に60歳以上の80%が感染していると言われています。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの消化性潰瘍はピロリ菌感染者の10~15%程度、またピロリ菌に感染して数十年の間に3~5%程度が胃がんを発症しています。みぞおちなど腹部や背中の痛み・腹部不快感・胸やけや吐き気などの自覚症状は、空腹時や食後少し時間がたってからおこる場合が多く、軽い食事の後は痛みがなくなる傾向にあります。一方、全く自覚症状がなく人間ドックなどで偶然発見される場合もあります。
感染を調べる方法としては、胃内視鏡検査・呼気検査・血中抗体検査・便抗原検査等があります。自覚症状のある方は検査を受けておくと安心です。症状がなくても、胃がんの早期発見のためには50歳以上の方は2年に1回の胃内視鏡検査が推奨されています。感染がみとめられた場合、一般的に1日2回7日間の内服により70%以上の方がピロリ菌除菌に成功します。効果がみられなかった場合でも2回目の除菌で90%が治癒できます。内服を指示されたとおりにきちんと守ること、また、日頃から過労やストレスを避け規則正しい食生活を心がけることが大切です。
花粉症の季節です(2020年2月)

花粉症は、花粉が原因で様々な症状が生じる季節性のアレルギー疾患です。最も多いのはスギ花粉症ですが、スギ花粉症の方の8割はヒノキ花粉症も合併しています。スギ花粉は2~4月、ヒノキ花粉は4~5月頃に多く飛散します。前年の夏、特に6~7月の日照時間が長いほど多く飛ぶ傾向にあります。身体内に取り込まれると身体にとって異物である花粉を排除しようと炎症を誘発するヒスタミンやロイコトリエンといった物質が放出され、これによって、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみ等の症状が生じます。
治療は、抗ヒスタミン薬などの薬物療法、鼻づまりに効果がある鼻の空気の通りを広くするレーザー治療、原因となっているアレルゲンを少量ずつ与え続け身体に慣れさせることによりアレルギー反応を起こさないようにする減感作療法と、大きく分けると3つあります。減感作療法のなかでも口に薬を入れる舌下免疫療法は体質改善するのに有効ですが、花粉の飛んでいない時期から始める必要があります。
症状を軽くするには、規則正しい食生活が基本です。その中でも、乳酸菌飲料やヨーグルト、食物繊維を多く含むごぼうやれんこんなどの根菜類、インゲンやバナナなどのオリゴ糖を含む食品を意識して摂り、免疫機能と関係の深い腸内の善玉菌を増やし腸内環境を整えることが大切です。粘膜を強くする働きのあるビタミンAを多く含むニンジンやホウレンソウなどの緑黄色野菜もしっかり摂ることをお勧めします。身体内に入る花粉を少しでも減らすために、外出時にはマスクや眼鏡、帽子の着用をしましょう。帰宅したら玄関に入る前に花粉を払い、うがいや洗顔を普段から習慣化しておいて下さい。
低血圧と立ちくらみ(2020年1月)
 血圧は、ポンプの役割を担う心臓の収縮によって血液が全身に送り出される際に血管に加わる圧力のことです。一般的に収縮期血圧(上の血圧)が100mmHg以下を低血圧と呼びます。低血圧には種類があり、特に原因となる疾患がなく血圧の低い状態が続く本態性低血圧、心疾患や内分泌・代謝疾患などによる症候性低血圧、急に座ったり立ったりといった体位交換をした時におこる起立性低血圧があります。血圧を一定に保とうとする身体のしくみがうまく働かないためにおこる起立性低血圧は思春期や高齢者に多くみられます。
血圧は、ポンプの役割を担う心臓の収縮によって血液が全身に送り出される際に血管に加わる圧力のことです。一般的に収縮期血圧(上の血圧)が100mmHg以下を低血圧と呼びます。低血圧には種類があり、特に原因となる疾患がなく血圧の低い状態が続く本態性低血圧、心疾患や内分泌・代謝疾患などによる症候性低血圧、急に座ったり立ったりといった体位交換をした時におこる起立性低血圧があります。血圧を一定に保とうとする身体のしくみがうまく働かないためにおこる起立性低血圧は思春期や高齢者に多くみられます。
朝起きるのがつらかったり、急に立った時に血の気がひくという一般的な症状の他、疲れやすい・頭が重い・めまい・耳鳴り・動悸・吐き気など自覚症状は様々です。立ちくらみは、一時的に脳への血流が減少した結果生じる循環不全によっておこるため、健康な人でもおこることがあります。
本態性低血圧と起立性低血圧については、自律神経の調節がうまく働かないために起こります。予防と改善には、十分な睡眠と規則正しい生活が基本です。三食栄養バランスのとれた食事と水分摂取をこまめにおこなうことも大切です。全身の循環を良くするために、ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動が効果的です。
起き上がる時はゆっくりとおこなうよう意識し、起立時の下肢末梢静脈血液のうっ滞を防ぐため弾力ストッキングを装着した方が良い場合もあるため、日常生活に気を付けても改善しない場合は、早めに受診しご相談してください。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)=タバコ病(2019年12月)
 喉からつながっている空気の通り道である気管が左右に枝分かれして気管支となります。細くなった気管支の先端には、小さな袋状の肺胞が3~4億個付着し、ここで酸素と二酸化炭素の交換をおこないます。気管から細気管支までを気道といい、気道と肺胞を併せたものが肺です。慢性閉塞性肺疾患は、慢性気管支炎や肺気腫等の総称で、タバコの煙を主とする有機物質を長期に吸入暴露することで生じる肺の炎症性疾患です。Chronic(慢性・いつも)Obstructive(閉塞性・気道が狭くなる)Pulumonary(肺の)Disease(疾患・病気)の頭文字を取ってCOPD(シーオーピ-ディ)と呼ばれています。気道がむくんだり気管支の中に痰がたまったりして炎症が進行し、肺が正常な状態に戻らなくなるため、運動をしたわけでもないのに呼吸が苦しくなって息切れがする等の症状があらわれ、重症化すると常に酸素ボンベが必要となり、生活の質を低下させます。
喉からつながっている空気の通り道である気管が左右に枝分かれして気管支となります。細くなった気管支の先端には、小さな袋状の肺胞が3~4億個付着し、ここで酸素と二酸化炭素の交換をおこないます。気管から細気管支までを気道といい、気道と肺胞を併せたものが肺です。慢性閉塞性肺疾患は、慢性気管支炎や肺気腫等の総称で、タバコの煙を主とする有機物質を長期に吸入暴露することで生じる肺の炎症性疾患です。Chronic(慢性・いつも)Obstructive(閉塞性・気道が狭くなる)Pulumonary(肺の)Disease(疾患・病気)の頭文字を取ってCOPD(シーオーピ-ディ)と呼ばれています。気道がむくんだり気管支の中に痰がたまったりして炎症が進行し、肺が正常な状態に戻らなくなるため、運動をしたわけでもないのに呼吸が苦しくなって息切れがする等の症状があらわれ、重症化すると常に酸素ボンベが必要となり、生活の質を低下させます。
肺機能は20歳代がピークで、健康な方でもその後は低下しますが、喫煙者は2倍のスピードで衰えます。40歳以上の10人に1人、約530万人がCOPDを患っています。進行すると治療しても肺機能は元にもどらないため、症状が出ていなくても肺のレントゲン検査や肺機能検査を定期的に受けておくと安心です。
予防するためには禁煙が最も大切です。タバコをやめれば、その後の肺機能の低下は吸わない人とほぼ同じになります。禁煙治療には健康保険が適用されますので、無理なく禁煙が可能です。他人のタバコの煙を吸う受動喫煙でもCOPDになる危険があります。ご家族や従業員、友人のためにも是非とりくんで下さい。
インフルエンザ対策(2019年11月)
 インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症でA型・B型・C型に大きく分けられ、今年はA型が約90%、B型が約10%の流行が予測されています。感染経路としては、つり革やドアノブ・スイッチなどを手指で触ることにより介する接触感染、ウイルスを含んだ咳やくしゃみを介する飛沫感染、感染した人が吐いた息に含まれるウイルスが付着した粒子が長時間空気中に漂い、それを吸い込むことによるエアゾル感染があります。感染すると、喉の痛みや鼻水などの風邪の症状に加え、高熱や関節痛などの全身症状が急速に現れますが、軽症の場合は症状がでないこともあります。高齢者や持病のある方は重症化しやすいため注意が必要です。
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症でA型・B型・C型に大きく分けられ、今年はA型が約90%、B型が約10%の流行が予測されています。感染経路としては、つり革やドアノブ・スイッチなどを手指で触ることにより介する接触感染、ウイルスを含んだ咳やくしゃみを介する飛沫感染、感染した人が吐いた息に含まれるウイルスが付着した粒子が長時間空気中に漂い、それを吸い込むことによるエアゾル感染があります。感染すると、喉の痛みや鼻水などの風邪の症状に加え、高熱や関節痛などの全身症状が急速に現れますが、軽症の場合は症状がでないこともあります。高齢者や持病のある方は重症化しやすいため注意が必要です。
日常生活では手洗いとマスクが基本で、アルコール手指消毒剤の使用も有効です。手洗いは、手の甲・指先・爪と指の間と手首も忘れずに石けんやハンドソープで丁寧に洗いましょう。普段から栄養バランスの良い食事と十分な睡眠を心がけ、規則正しい生活で体調を整えウイルスへの抵抗力を維持しておきましょう。
ワクチンを接種すると発症を50~60%減少させることができ、発症した場合にも重症化を防ぐ効果が期待できます。ワクチン接種の2週間後くらいから抗体が増え始め、1~2ヶ月後にピークを迎えます。今年は例年より早めに流行する可能性が高く、予防接種も早めに受けておくと安心です。高齢者の方は肺炎の合併症予防のために肺炎球菌ワクチンの接種を受けることも勧められているため、主治医の先生にご相談ください。
ご家族が感染した場合は、なるべく同じ部屋で過ごさないようにするとともに、十分な換気を忘れずにおこないましょう。
食後高血糖と隠れ糖尿病(2019年10月)
 糖尿病は、膵臓からでる血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの作用不足により血糖が慢性的に多い状態で、血管を傷つけ網膜症や腎不全などの合併症をおこすことがあります。
糖尿病は、膵臓からでる血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの作用不足により血糖が慢性的に多い状態で、血管を傷つけ網膜症や腎不全などの合併症をおこすことがあります。
食事で摂取されたブドウ糖は腸で吸収され血液中に移行するため、食事をすると一時的に血糖値が上昇します。健康な人の場合、食後2から3時間で血糖値は空腹時の値に戻っていきますが、インスリンの分泌量が少なかったり働きが十分でない耐糖能異常の状態は、血糖値が140mg/dl以上の高い値が続き、食後高血糖といいます。通常は緩やかに上昇する血糖値が食後急激に変動し、グラフにするとスパイク(くぎ)のようにとがった線を描くので、血糖値スパイクとも呼ばれています。時間がたつと正常値に戻るため気付かないまま放置してしまう危険があり、糖尿病を発症したり進行したりするため、動脈硬化を促進させ心筋梗塞や脳卒中などの大血管障害を起こすリスクが高くなります。早期発見には、ブドウ糖負荷試験検査で食後高血糖を調べると良いでしょう。また、過去1~2か月の平均血糖値を示すHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)値が高い場合は食後血糖値も高い可能性があるといわれています。
早食いはインスリンの働きが追いつかなくなるため、ゆっくり食事を摂りましょう。ブドウ糖の吸収を緩やかにする野菜や海藻を最初に食べると、血糖値の急激な上昇を防げます。食後30分から1時間くらいは血糖値が上がりやすいため、そのタイミングでブドウ糖を消費する運動すると効果的です。散歩や体操、階段昇降等、食後に10~15分程度、身体を動かす習慣をもつことをお勧めします。
