こんにちは保健師です!
逆流性食道炎(2021年3月)
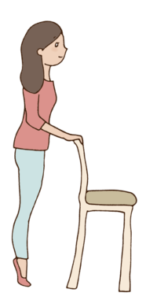
胃の中で胃液と混ざり合った食べ物や胃液そのものが食道に逆流すると、胃液は強い酸性のため、食道に逆流すると粘膜にびらん(ただれ)や潰瘍ができます。
主な原因としては、食道と胃のつなぎめにあたる下部食道括約筋の筋力低下があげられます。加齢、便秘や肥満により腹圧が高まることで筋力は低下し、高齢者だけでなく若い人でも罹る病気です。また、脂肪の多い食事をすると胃酸が増え消化に時間がかかるため、下部食道括約筋にも負担となり筋力低下につながります。
胃酸の逆流は食後2~3時間後におこるため、自覚症状も食後に起こりやすくなります。胸やけ、すっぱいものがこみ上げてくる、胃もたれや痛み、喉にイガイガするような違和感、慢性的な咳などの症状がある場合には、内視鏡検査を受けると早期に発見できます。放置すると、誤嚥性肺炎や食道がんを発症することもあるため注意が必要です。
食べ過ぎに注意し、特に脂っこい物ばかり食べないようにすることが大切です。過度の飲酒や喫煙も胃酸の逆流に影響を及ぼすことがあります。食後すぐに横にならない、お腹を圧迫しない、前かがみの姿勢を避ける等も日常生活の中で心がけておきましょう。横になる場合は、左側を下にして寝ると胃の内容物が逆流しないようになります。
便秘の予防と解消のために、野菜や水分をしっかりとること、ウォーキングやストレッチ等で血行を良くすることが効果的です。便意がなくても毎日トイレに座る時間を持つようにしましょう。腹筋やつま先立ちなどでお腹まわりの筋肉を強化しておくこともお勧めです。
春は自律神経の乱れに注意(2021年2月)

交感神経と副交感神経という二つの自律神経がバランスをとりながら、身体の動きを調整しています。春は1年のうちで寒暖差が一番大きく、気温の変化に対応するため身体は交感神経の働きが優位な緊張状態が続きやすくなります。
心身を活発にする交感神経が働くと、たくさんのエネルギーが消耗され疲れやだるさを感じやすくなります。低気圧の影響で血液中の酸素濃度が下がり、日中の眠気や身体のだるさを感じやすくなることもあります。冬に比べて日照時間が長くなるため、朝早く目が覚めたり夜更かしが増えたりすると、心身を休め回復させる副交感神経の働きが悪くなり、朝起きた時の疲労感やめまい・耳鳴り・立ちくらみなどを起こす場合もあります。このような症状は複数同時にあらわれたり、日によって軽かったり重かったりし、コントロールが難しくなります。
食事を摂ると消化のために副交感神経が働き、身体はリラックスモードになります。欠食や偏食は避け、バランスの良い食事を普段から心がけましょう。自律神経を整える作用のあるビタミンC(果物・いも類など)・ビタミンA(緑黄色野菜・卵など)・ビタミンE(ナッツ類・魚介類など)・カルシウム(乳製品・豆腐やごまなど)を積極的に摂りましょう。運動をすると自律神経のバランスを整えるセロトニンというホルモンが分泌されます。ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動が効果的です。普段から、歩幅を広げて歩く・こまめに動く・階段を使用するなど、日常生活の中で工夫して動く習慣を持っておくことが大切です。入浴やシャワーだけでなく10~20分湯船につかり、深い眠りを誘うために目元や首元を40度くらいの蒸しタオルやアイマスクで温めると、睡眠の質が良くなります。
寒い季節の血栓症(2021年1月)
 血栓は、血液が固まってできるかたまりのことです。血栓が血管をふさぐと全身を循環している血液の流れがとまり、臓器に酸素や栄養が送られなくなって臓器が壊死してしまうことを梗塞といい、こうして引き起こされる病気のことを総称して血栓症といいます。
冬になると、心筋梗塞や脳梗塞による死亡者数は夏に比べ約1.5倍になります。気温が下がると身体は血管を収縮させて体温を維持しようとします。血管が細くなると他の季節では問題とならなかったような血栓でも寒い冬場はそれが血行不全の原因となることと、細くなった血管内で血流を維持しようとして血圧が上昇することも血栓症の誘因となります。また、冬場は湿度が低く乾燥するため、身体から水分が奪われて脱水になりやすく、血液が粘調になり固まりやすくなることも血栓が生じやすくなります。
喉が渇いていなくても、1時間に100ml程度のこまめな水分補給をおこないドロドロ血液を防ぐよう心がけてください。血圧の乱高下による身体への負担を防ぐために、外出や入浴時等の寒暖差に注意しましょう。
血流を良くしておくために、1日20分程度のウォーキングなどの運動を日頃からおこない、体重管理や血圧管理が大切です。脂っこい食事はさけ、脂質の代謝を促進させるビタミンBを多く含む食品(豚肉や豆類など)や、EAPやDHAを多く含む青魚などを積極的に摂りましょう。
喫煙は、血管内の炎症をおこし動脈内の血栓を急激に発生させることがあるため、禁煙は基本です。
血栓は、血液が固まってできるかたまりのことです。血栓が血管をふさぐと全身を循環している血液の流れがとまり、臓器に酸素や栄養が送られなくなって臓器が壊死してしまうことを梗塞といい、こうして引き起こされる病気のことを総称して血栓症といいます。
冬になると、心筋梗塞や脳梗塞による死亡者数は夏に比べ約1.5倍になります。気温が下がると身体は血管を収縮させて体温を維持しようとします。血管が細くなると他の季節では問題とならなかったような血栓でも寒い冬場はそれが血行不全の原因となることと、細くなった血管内で血流を維持しようとして血圧が上昇することも血栓症の誘因となります。また、冬場は湿度が低く乾燥するため、身体から水分が奪われて脱水になりやすく、血液が粘調になり固まりやすくなることも血栓が生じやすくなります。
喉が渇いていなくても、1時間に100ml程度のこまめな水分補給をおこないドロドロ血液を防ぐよう心がけてください。血圧の乱高下による身体への負担を防ぐために、外出や入浴時等の寒暖差に注意しましょう。
血流を良くしておくために、1日20分程度のウォーキングなどの運動を日頃からおこない、体重管理や血圧管理が大切です。脂っこい食事はさけ、脂質の代謝を促進させるビタミンBを多く含む食品(豚肉や豆類など)や、EAPやDHAを多く含む青魚などを積極的に摂りましょう。
喫煙は、血管内の炎症をおこし動脈内の血栓を急激に発生させることがあるため、禁煙は基本です。
風邪予防(2020年12月)
 コロナ禍が続く中、これからの季節は風邪やインフルエンザの流行が本格化し、例年以上にウイルス対策の徹底が求められています。手洗い・うがい・マスクの着用は基本ですが、風邪などを引き起こすウイルスは、低温で乾燥した場所を好むため、室温を20度前後、湿度は70%前後に保ち、加湿器をつかったり、濡らした衣服を干したりするなどの工夫も大切です。外出時は、マフラーや手袋などを上手に活用し、首や袖、足元など衣服の開口部をしっかりふさぐと身体の熱が逃げにくくなり、保湿効果が高まります。
日頃から免疫力があがる食材を摂るよう意識しましょう。柑橘類や野菜に多く含まれているビタミンCは免疫力を保つ働きがあります。レバーやにんじんなどに多く含まれているビタミンAは、ウイルスなどの侵入口である粘膜の健康を保ちます。ホウレンソウなどの青菜類やブロッコリーやかぼちゃなどはビタミンA・Cともに多く含みます。免疫細胞の約70%が存在する腸の環境を整えるために納豆などの発酵食品もお勧めです。
寒暖差があると交感神経が刺激され寝つきが悪くなるため、質の良い睡眠のためには、寝る1時間前には暖房を入れたりして寝室を温めておきましょう。38~40度のぬるめのお湯で15~20分の半身浴(お湯は胸の下くらいまで)も身体が温まり、寝つきが良くなります。身体を動かすことは大切ですが、急激な温度変化は脳や心臓に負担がかかるため、早朝や起床直後の運動は避けましょう。激しい運動は免疫細胞を減少させることがあるため、ウォーキングなどの有酸素運動やストレッチやスクワットなどの筋トレをほどほどに毎日続けることがポイントです。
コロナ禍が続く中、これからの季節は風邪やインフルエンザの流行が本格化し、例年以上にウイルス対策の徹底が求められています。手洗い・うがい・マスクの着用は基本ですが、風邪などを引き起こすウイルスは、低温で乾燥した場所を好むため、室温を20度前後、湿度は70%前後に保ち、加湿器をつかったり、濡らした衣服を干したりするなどの工夫も大切です。外出時は、マフラーや手袋などを上手に活用し、首や袖、足元など衣服の開口部をしっかりふさぐと身体の熱が逃げにくくなり、保湿効果が高まります。
日頃から免疫力があがる食材を摂るよう意識しましょう。柑橘類や野菜に多く含まれているビタミンCは免疫力を保つ働きがあります。レバーやにんじんなどに多く含まれているビタミンAは、ウイルスなどの侵入口である粘膜の健康を保ちます。ホウレンソウなどの青菜類やブロッコリーやかぼちゃなどはビタミンA・Cともに多く含みます。免疫細胞の約70%が存在する腸の環境を整えるために納豆などの発酵食品もお勧めです。
寒暖差があると交感神経が刺激され寝つきが悪くなるため、質の良い睡眠のためには、寝る1時間前には暖房を入れたりして寝室を温めておきましょう。38~40度のぬるめのお湯で15~20分の半身浴(お湯は胸の下くらいまで)も身体が温まり、寝つきが良くなります。身体を動かすことは大切ですが、急激な温度変化は脳や心臓に負担がかかるため、早朝や起床直後の運動は避けましょう。激しい運動は免疫細胞を減少させることがあるため、ウォーキングなどの有酸素運動やストレッチやスクワットなどの筋トレをほどほどに毎日続けることがポイントです。
冷えと関節痛(2020年11月)
 関節痛は、長い時間同じ姿勢をしていた時や朝起きた時に感じることが多く、ひじや膝、指などに起こりますが、特に膝の関節には常に体重の4~6倍の負荷がかかっているため関節痛が起こりやすい部位です。原因の1つに変形性膝関節症があげられますが、これは膝の関節の軟骨が摩擦などですり減る慢性的な炎症や変形が起こる病気です。寒い時期は血管が収縮することにより体温が低下し関節や末端などの冷えを引き起こすため、血流不足によって軟骨などに栄養もいきわたりにくくなることや筋肉の緊張やこりによっても痛みを感じやすくなるため、冷えを取り除くことが関節痛緩和につながります。
お風呂でじっくりと全身を温めたり、患部をサポーターなどで保護すると冷え取りになります。膝周りのストレッチや膝をささえる筋肉を鍛えると血流改善や熱産生につながります。ただし、痛みが強い時は無理に運動したり温めたりせず、腫れや炎症がある時は早めに受診しましょう。
日頃から正しい歩き方を習慣づけ、お尻の筋肉である大殿筋と、股関節を閉じる働きを担っている筋肉である内転筋を鍛えると、膝の痛みの予防になります。背筋を伸ばし歩幅を大きくとるようにして、膝が自然と伸びるようにかかとから着地する歩き方を心がけましょう。信号やエレベーターを待っているちょっとの時間に片足立ちをしたり、椅子に腰かけ片足ずつ上げる運動も効果的です。正座やあぐらといった膝に負担をかける座り方は避け、適正体重の維持も重要です。軟骨を形成しているグルコサミンを多く含むカニやエビなどの甲殻類や、ヒアルロン酸を含む牛・豚・鶏肉の軟骨やきのこ類、おくらなどを意識して摂りましょう。
関節痛は、長い時間同じ姿勢をしていた時や朝起きた時に感じることが多く、ひじや膝、指などに起こりますが、特に膝の関節には常に体重の4~6倍の負荷がかかっているため関節痛が起こりやすい部位です。原因の1つに変形性膝関節症があげられますが、これは膝の関節の軟骨が摩擦などですり減る慢性的な炎症や変形が起こる病気です。寒い時期は血管が収縮することにより体温が低下し関節や末端などの冷えを引き起こすため、血流不足によって軟骨などに栄養もいきわたりにくくなることや筋肉の緊張やこりによっても痛みを感じやすくなるため、冷えを取り除くことが関節痛緩和につながります。
お風呂でじっくりと全身を温めたり、患部をサポーターなどで保護すると冷え取りになります。膝周りのストレッチや膝をささえる筋肉を鍛えると血流改善や熱産生につながります。ただし、痛みが強い時は無理に運動したり温めたりせず、腫れや炎症がある時は早めに受診しましょう。
日頃から正しい歩き方を習慣づけ、お尻の筋肉である大殿筋と、股関節を閉じる働きを担っている筋肉である内転筋を鍛えると、膝の痛みの予防になります。背筋を伸ばし歩幅を大きくとるようにして、膝が自然と伸びるようにかかとから着地する歩き方を心がけましょう。信号やエレベーターを待っているちょっとの時間に片足立ちをしたり、椅子に腰かけ片足ずつ上げる運動も効果的です。正座やあぐらといった膝に負担をかける座り方は避け、適正体重の維持も重要です。軟骨を形成しているグルコサミンを多く含むカニやエビなどの甲殻類や、ヒアルロン酸を含む牛・豚・鶏肉の軟骨やきのこ類、おくらなどを意識して摂りましょう。
インフルエンザとコロナ対策(2020年10月)

インフルエンザは、インフルエンザウイルスにより引き起こされる急性ウイルス性疾患です。例年11月頃から徐々に増え始め、1月頃に流行がピークに達し4月過ぎに収束する傾向があります。新型コロナウイルスに関しても、夏季より冬季に大きな流行を起こす可能性があるため、手洗い、咳エチケット、密閉・密集・密接の3密を避けるなどの感染症対策を今後も継続しましょう。
主症状として高熱のでるインフルエンザは潜伏期が1~2日、ウイルス排出のピークは発病後2~3日ですが、発熱に加えて味覚や臭覚の異常を伴うことのある新型コロナは、潜伏期間が1~14日と長く、ウイルスの排出ピークは発病の1日前と、無症状の知らないうちに他の人にうつす可能性があることが特徴的です。インフルエンザと新型コロナの混合感染や重症化についてはまだ報告されていませんが、特に高齢者や持病のある方はインフルエンザワクチンの接種を早めにすませておくと安心です。
日頃から免疫力アップを心がけ、体調を整えておくことが大切です。免疫にかかわるビタミンDは、日光にあたることで皮膚から吸収されるため、ウォーキングなどの運動がお勧めです。食品では鮭やサバ・マグロなどの魚介類やキノコ類、レバーやチーズなどに多く含まれますので、日頃の食事の中で意識して摂るようにして下さい。免疫細胞の主要成分は良質なたんぱく質です。肉や魚の他、大豆製品や卵・乳製品もしっかり摂りましょう。免疫細胞の60~70%は腸管に集まっているため、納豆やみそなどの発酵食品や海藻などの食物繊維で腸内環境を整えておくことも効果的です。
疲労やストレス、睡眠不足は免疫力を低下させます。日常生活の中で出来ることから改善し、インフルエンザや新型コロナに負けずに今年の冬を乗り切りましょう。
認知症になる前に・・(2020年9月)

65歳以上の5人に1人は認知症になると言われていますが、高齢者だけの病気ではなく、若いうちからリスクは蓄積されています。アルツハイマー型認知症の原因となるアミロイドβ(脳内異常たんぱく質)は、発症の25年前から蓄積が始まり、ゆっくりと進行していきます。脳血管性認知症においては、高血圧や糖尿病などの生活習慣病によって発症の可能性が高まります。また、糖尿病の人がアルツハイマー型認知症を発症するリスクは糖尿病でない人と比べると4.6倍も高くなっています。
発症の前段階である軽度認知障害で気づき、治療や生活習慣改善をすることが、認知症発症を食い止めたり遅らせることに有効です。普段の生活の中で、約束したことをよく忘れる・物を失くしたり置忘れやしまい忘れが増えた・物や人の名前が出てこない・今まで好きだった趣味への興味がなくなった・新しいことに関心がなくなり覚えようとしなくなった等に当てはまる場合は、かかりつけ医または神経内科・脳外科、心療内科・物忘れ外来などを早めに受診しましょう。
人との交流や会話は脳を刺激し、認知症予防につながります。家族や同僚・地域の仲間との会話はとても有効です。定期的な運動は血流を良くし、脳への適度な刺激にもなります。週3日程度30分ほどの運動を生活の中にとりいれてたり、抗酸化作用のあるビタミンC・Eやβカロチンが含まれている果物や野菜、DHAやEAPが含まれている青魚を積極的に摂りましょう。睡眠不足は脳のダメージにつながります。質の良い睡眠をしっかりとり、朝は日光を浴びて体内時計をリセットする等、規則正しい生活が基本です。
正しく理解し、結核から身を守ろう(2020年8月)
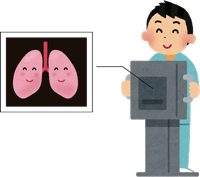
結核は結核菌に感染する病気です。昭和20年代までは国民病と言われ、約50年前までは年間死亡者数が10数万人に及び、死亡原因の1位でした。今でも1日50人程度の新患者が発生し、5人が命を落としている重大な感染症の1つで、決して過去の病気ではありません。厚生労働省や地方自治体等では、毎年9月の最終週を結核予防週間として、知識の普及啓発をおこなっています。
咳やくしゃみなどの空気感染でうつりますが、感染しても発病するのは10人に1~2人程度です。感染後すぐに発病することもあれば、何十年後かに身体の抵抗力が衰えた時に発病することもあります。発病する約90%は肺結核ですが、結核菌は肺以外の臓器も侵すため、脊椎カリエス・結核性胸膜炎・腎結核などの全身に病巣ができることがあります。
初期症状は、咳や痰・微熱・倦怠感・体重減少などで、血痰や胸痛・息切れなどの症状がでることもあります。結核と診断されても、6~9か月間の内服で治りますので、早期発見・早期治療が大切です。
発症を予防するためには、十分な睡眠、バランスのとれた食事、運動の習慣化という、免疫の働きを保つ規則正しい生活を心がけましょう。無理なダイエットや喫煙、糖尿病及び人工透析治療をおこなっている方やステロイド剤を飲んでいる方等は発症リスクが高くなりますので、持病のコントロールと禁煙は基本です。
自身の健康のためだけでなく、知らないうちに周囲にうつすことのないよう、年1回は健診を受診し、胸部レントゲン検査をうけましょう。健診は、毎年時期を決めて早めに予定し、必ず受診することが健康への近道です。
歩幅を伸ばしてサルコペニアを予防しよう(2020年7月)

サルコペニアとは、ギリシャ語で筋肉を意味する「サルコ」、喪失を意味する「ペニア」を合わせた造語で、全身の筋肉量と筋力が低下し身体能力が低下した状態と定義されています。加齢による筋肉量減少が原因とされる一次性サルコペニアと、加齢以外の活動量や内臓疾患、栄養不良等による二次性サルコペニアに分類されます。
サルコペニアは、たんぱく質の摂取量及び運動量の減少によって、つくられる筋肉よりも分解される筋肉の方が多くなることが原因でおこりますが、人は誰でも40歳を境に徐々に筋肉量が減少していく傾向があり、60歳を過ぎるとその減少率は加速します。この減少率を最小限におさえるためには、適度な運動と栄養バランスのとれた食事が大切です。
運動は筋トレとウォーキングなどの有酸素運動を組み合わせると効果的です。筋肉量を減らさないウォーキングの方法は、普段の歩幅プラス10cmを意識するとよいと言われています。歩幅が大きくなると自然にスピードが上がり、筋肉に刺激が与えられ、筋トレ効果が期待できます。歩いているうちに元の歩幅に戻ってしまっても、「歩幅プラス10cm」を思い出して歩き直しましょう。
食事では、筋肉生成に効果のあるたんぱく質が豊富な肉や魚、大豆、卵などの食材を中心に、筋肉を動かすエネルギー源となる炭水化物(米・パン・麺類)、たんぱく質の働きを助けるビタミンB6(マグロの赤身・レバー・鰹・鶏ささみ・キウイ・バナナ)などを意識して食べるよう心がけてください。
ふくらはぎがつる原因と対策(2020年6月)
 運動や睡眠中などに急にこむら返りをおこすことがあります。こむら返りはふくらはぎの腓腹筋や神経が異常な緊張をおこし、筋肉が収縮したまま弛緩しない状態になるため激しい痛みを伴う腓腹筋痙攣のことで、一般的に「足がつる」という言い方をします。
食生活の偏りや脱水等により身体内の水分や電解質の不足によって筋肉が十分な代謝をおこなうことが出来なくなったり、疲れや冷え等による血流不足が原因でおこることが多く、糖尿病や甲状腺機能低下症などの代謝異常や腰椎の変形などで脊椎神経を圧迫することによりおこる場合もあります。
応急処置としては、患部を伸ばすことです。足の指を持ち身体の方へと引き寄せたり、壁に足の裏を押し付けて、アキレス腱を伸ばしましょう。無理やり一気に伸ばすと筋肉が損傷し肉離れをおこすことがあるため、慎重にゆっくり伸ばすようにしてください。
慢性的なこむら返りは運動不足によるものが多いため日頃からストレッチなどをおこない血流を良くしておくことと、十分な睡眠で疲労をためない事が大切です。足湯や厚手の靴下などで足が冷えないように気を付けましょう。筋肉の動きをスムーズにする働きをもつカルシウムを多く含む乳製品や魚介類・大豆製品を意識して摂るよう心がけてください。疲労回復を促進するビタミンB1を多く含むうなぎや卵・豚肉、クエン酸を含むレモンや酢などもお勧めです。
腰痛や脚がむくみやすい、喉が渇くなどの自覚症状が普段からある場合は、かかりつけ医や神経内科、整形外科等を早めに受診しご相談してください。
運動や睡眠中などに急にこむら返りをおこすことがあります。こむら返りはふくらはぎの腓腹筋や神経が異常な緊張をおこし、筋肉が収縮したまま弛緩しない状態になるため激しい痛みを伴う腓腹筋痙攣のことで、一般的に「足がつる」という言い方をします。
食生活の偏りや脱水等により身体内の水分や電解質の不足によって筋肉が十分な代謝をおこなうことが出来なくなったり、疲れや冷え等による血流不足が原因でおこることが多く、糖尿病や甲状腺機能低下症などの代謝異常や腰椎の変形などで脊椎神経を圧迫することによりおこる場合もあります。
応急処置としては、患部を伸ばすことです。足の指を持ち身体の方へと引き寄せたり、壁に足の裏を押し付けて、アキレス腱を伸ばしましょう。無理やり一気に伸ばすと筋肉が損傷し肉離れをおこすことがあるため、慎重にゆっくり伸ばすようにしてください。
慢性的なこむら返りは運動不足によるものが多いため日頃からストレッチなどをおこない血流を良くしておくことと、十分な睡眠で疲労をためない事が大切です。足湯や厚手の靴下などで足が冷えないように気を付けましょう。筋肉の動きをスムーズにする働きをもつカルシウムを多く含む乳製品や魚介類・大豆製品を意識して摂るよう心がけてください。疲労回復を促進するビタミンB1を多く含むうなぎや卵・豚肉、クエン酸を含むレモンや酢などもお勧めです。
腰痛や脚がむくみやすい、喉が渇くなどの自覚症状が普段からある場合は、かかりつけ医や神経内科、整形外科等を早めに受診しご相談してください。
