こんにちは保健師です!
熱中症に気をつけましょう(2024年6月)
 熱中症は、高温多湿な場所で、身体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かなること等により、熱がこもった状態のことです。真夏の時期だけでなく、春や秋でも急に暑くなった時や身体がまだ暑さに慣れていない時に引き起こすこともあります。入院された方の半数以上は、炎天下ではなく日常生活の中で発症しており、家の中にいても注意が必要です。
熱中症は、高温多湿な場所で、身体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かなること等により、熱がこもった状態のことです。真夏の時期だけでなく、春や秋でも急に暑くなった時や身体がまだ暑さに慣れていない時に引き起こすこともあります。入院された方の半数以上は、炎天下ではなく日常生活の中で発症しており、家の中にいても注意が必要です。
軽度の場合は、めまいやだるさ・手足のしびれ・なんとなく気分が悪い等の症状がみられ、重くなるにつれて、吐き気・頭痛・身体に力が入らない・意識がなくなる等がおこることがあります。重症の場合は命にかかわる病気ですので、早めの受診が大切です。
屋外では日傘や帽子を使用し、日陰でこまめに休憩をとるよう心がけてください。屋内では部屋を閉め切らないことが重要で、室内に風を通すようにしましょう。建物の温度上昇を抑えるには、南側にゴーヤやヘチマ、あさがおなどの植物を植えたり、打ち水をすることも効果的です。風通しを良くしていても室温が28度を超えるような場合は、クーラーなどで調節する必要があります。
屋外・屋内にかかわらず、こまめな水分摂取は大切です。特に運動や力仕事をする20~30分前にはコップ1杯を忘れずに飲みましょう。水に少量の食塩(1リットルに対し小さじ1/3)やレモン汁を入れたりして、水分だけでなく電解質も摂ると良いでしょう。高齢者は脱水になりやすいだけでなく、自分では気が付きにくいことが多いため、時間をきめて経口補水液を飲む習慣があると安心です。熱中症は自己管理で予防できる疾患です。日頃から、睡眠や栄養を十分とり、体力をつけておくことも予防につながります。
RSウイルス感染症(2024年5月)
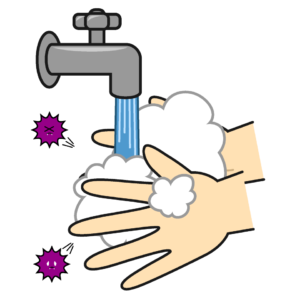 RSウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症は、2歳までにほぼすべての子どもに感染するとされています。その後も生涯にわたって何度も感染と発症を繰り返したり、何度も感染を繰り返して症状が軽くなることで罹っていることも知らずにいる場合もあります。潜伏期間は4~5日で、鼻水や咳などの風邪症状で発症し、多くの方は数日で回復します。発熱には個人差があり、38度以上の高熱が出たり、熱が上がったり下がったりする場合もあります。喘息や糖尿病、心臓病などの基礎疾患のある方や高齢者では、気管支炎や肺炎を引き起こすことがあり、60歳以上で毎年4500人程の方が亡くなっていて、注意が必要な感染症です。
RSウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症は、2歳までにほぼすべての子どもに感染するとされています。その後も生涯にわたって何度も感染と発症を繰り返したり、何度も感染を繰り返して症状が軽くなることで罹っていることも知らずにいる場合もあります。潜伏期間は4~5日で、鼻水や咳などの風邪症状で発症し、多くの方は数日で回復します。発熱には個人差があり、38度以上の高熱が出たり、熱が上がったり下がったりする場合もあります。喘息や糖尿病、心臓病などの基礎疾患のある方や高齢者では、気管支炎や肺炎を引き起こすことがあり、60歳以上で毎年4500人程の方が亡くなっていて、注意が必要な感染症です。
感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と、感染者との握手やドアノブや手すりなどを触ったりすることによる接触感染とがありますが、はしかや水ぼうそうのように空気感染はしません。感染者数は、近年では、春から初夏にかけて増加し夏にピークとなっています。特効薬はなく、症状にあわせた対症療法が基本となり、市販の解熱鎮痛剤や水分補給などで治ることが多いです。予防と対策には、鼻水や咳などの症状がある時にはマスクを着用し、日頃からのこまめな手洗いが重要です。石鹸と水で手指から手首にかけて20秒以上しっかり洗いましょう。睡眠や栄養などをしっかりとり、免疫力をつけておくことも大切です。家族に罹患者がいる場合は、洗面器やタオルなどの共有は避け、室内の定期的な換気を心がけてください。
任意接種となりますが、今年から60歳以上を対象とした感染予防のためのワクチン接種ができるようになりました。対象となる方は、かかりつけ医にご相談してください。
アルコールと脳卒中(2024年4月)
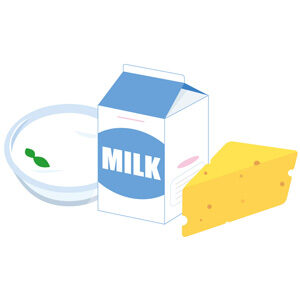 脳卒中には、血管がつまる脳梗塞と血管が破ける脳出血とがありますが、過度の飲酒は脳出血をおこしやすくなります。アルコールは1合20グラムですが、週300グラム以上飲むと、脳出血の発症リスクが高くなり、1日3合以上飲む人は、時々飲む人(月に1~3回程度)と比較して脳出血の発症率は2倍にもなります。
脳卒中には、血管がつまる脳梗塞と血管が破ける脳出血とがありますが、過度の飲酒は脳出血をおこしやすくなります。アルコールは1合20グラムですが、週300グラム以上飲むと、脳出血の発症リスクが高くなり、1日3合以上飲む人は、時々飲む人(月に1~3回程度)と比較して脳出血の発症率は2倍にもなります。
お酒を飲むと身体内に吸収されたアルコールが酵素によって酸化し、一時的に血圧が下がりますが、血圧が下がった状態で飲酒しつづけると、アルコールが肝臓で分解された時に発生する毒性のあるアセトアルデヒドが酸化されはじめることで、結果的に血中濃度が高くなり、血管は収縮して血圧の上昇につながります。よって、飲酒習慣のある方は高血圧による脳出血がおこりやすくなります。また、過度の飲酒は血液を固まりにくく作用もあり、飲酒量が増えるにつれ、出血性脳卒中の発症率は段階的に増えていきます。
適度な飲酒とは、一回量が純アルコール量20グラムまでです。ビール500ml・日本酒180ml・チューハイ350ml・ワイン200ml・焼酎100ml・ウイスキー60mlのうちいずれか一種類です。女性はこの半分の量が理想的です。
カルシウムの摂取量が不足すると、骨からの補給量が増えて血液中のカルシウム濃度が高くなり、血管を収縮させて血液の流れが悪くなり高血圧になりやすくなります。また、アルコールには利尿作用があり、飲みすぎると身体内に吸収されたカルシウムが必要な分まで排泄されてしまうこともあるため、吸収率の高い乳製品を日頃からしっかり摂るよう心がけましょう。
古くて新しい病気・肺結核(2024年3月)
 結核は、結核菌によって人から人にくしゃみなどによる飛沫感染でうつる慢性感染症です。昭和20年代頃までは、国民病と言われるほど流行していましたが、現在でも、全国では約1万人、東京都でも1千500人が毎年新たに患者報告がされています。人口10万人に対し、アメリカでは2.4%、ドイツでは5.0%に対し、日本は9.2%と高い罹患率で、誰でも罹る可能性があります。
結核は、結核菌によって人から人にくしゃみなどによる飛沫感染でうつる慢性感染症です。昭和20年代頃までは、国民病と言われるほど流行していましたが、現在でも、全国では約1万人、東京都でも1千500人が毎年新たに患者報告がされています。人口10万人に対し、アメリカでは2.4%、ドイツでは5.0%に対し、日本は9.2%と高い罹患率で、誰でも罹る可能性があります。
結核菌の潜伏期間は半年から2年で、感染した人が発病するのは1割から2割程度です。主に肺の内部で増えるため、咳・痰・発熱・呼吸困難などの風邪のような症状や、血痰・食欲低下・体重減少などが現れることもあります。また、肺だけでなく、腎臓、リンパ節、骨、脳など身体のあらゆる部分で病巣をつくることもあります。
2週間近く症状が続く場合は、かかりつけ医または呼吸器科を受診しましょう。知らないうちに罹っていることもあるため、症状がなくても、年1回はレントゲン検査を受けておくと安心です。発病した場合は、6か月から1年間、3~4種類の薬剤を内服する治療が基本で、2週間程度きちんと内服していれば他の人への感染はほぼなくなりますので、早めの受診を心がけてください。
感染しない・発病しないためには、普段から免疫力を高めておく必要があります。ウォーキングなどの有酸素運動は呼吸筋を鍛え肺年齢の強化になるため、今よりプラス1000歩を意識しましょう。バランスのとれた食事と十分な睡眠で、規則正しい生活を心がけてください。肺に直接負担のかかる喫煙はリスクが高いため、今すぐ禁煙にチャレンジしましょう。がんや糖尿病などの生活習慣病のある方は結核の発病率が高いため、生活習慣病の予防も大切です。
突発性難聴(2024年2月)
 突発性難聴は、突然、左右の耳の一方(ごくまれに両方)の聞こえが悪くなる疾患です。音を感じ取って脳に伝える役割をしている有毛細胞が傷つき壊れてしまうことでおこります。原因としては、糖尿病などの疾患による血流障害・ウイルス感染・ストレスや過労・睡眠不足などが考えられていますが、はっきりとしたことは明らかになっていません。子どもから高齢者までどの年代の方でも発症する可能性がありますが、特に40歳から60歳の働き盛りの年代に多く、治療を受けている人は年間で約3万5千人と言われいます。
突発性難聴は、突然、左右の耳の一方(ごくまれに両方)の聞こえが悪くなる疾患です。音を感じ取って脳に伝える役割をしている有毛細胞が傷つき壊れてしまうことでおこります。原因としては、糖尿病などの疾患による血流障害・ウイルス感染・ストレスや過労・睡眠不足などが考えられていますが、はっきりとしたことは明らかになっていません。子どもから高齢者までどの年代の方でも発症する可能性がありますが、特に40歳から60歳の働き盛りの年代に多く、治療を受けている人は年間で約3万5千人と言われいます。
聞こえにくさは人によって異なり、まったく聞こえなくなる人もいれば、高音だけ聞こえないという人もいます。高音だけ聞こえないタイプの方は、日常生活に必要な音は聞こえているため、難聴に気がつくのが遅れてしまいがちです。難聴の前後には、耳閉感、耳鳴り、めまいや吐き気を伴うことも多いのですが、この疾患は一度発症すると繰り返すことがないのも特徴です。ただし、発症後すぐに治療をしないと、耳鳴りが残ったり、聴力を失うこともあるため、早めの受診、目安として発症後1週間以内の適切な治療が必要です。
内耳の血流循環が悪くならないように、バランスの良い食事や十分な睡眠は日頃から意識しましょう。過度な飲酒や喫煙は避け、風邪やおたふくなどのウイルス感染を避けられるよう、健康状態を良好に保つことが大切です。ストレスを感じると交感神経が活発化することで、血管が収縮し血流不足につながります。ストレスは、過労や人間関係など数多くの要素があるため、自分なりのストレスの解消法を身につけておいてください。飛行機やダイビングなどの耳への負担も避けておくと安心です。
若くても誤嚥性肺炎に気をつけて(2024年1月)
 喉の奥は、空気を肺に送る気管と、飲食物を胃に送る食道のふたつに分かれていて、食べ物や飲み物を飲み込むと脳が指令を出して喉頭蓋が気管の入り口を塞ぎ、食道に流れて胃に送られるようになっています。しかし、飲み込む機能が弱くなると、飲食物が気管に入ってしまうことがあり、これを誤嚥といい、誤嚥した物と一緒に細菌が肺に入って炎症がおこったものが誤嚥性肺炎です。死亡率が高い高齢者の肺炎のうち7割以上を占めているため、早めの対策が必要です。
喉の奥は、空気を肺に送る気管と、飲食物を胃に送る食道のふたつに分かれていて、食べ物や飲み物を飲み込むと脳が指令を出して喉頭蓋が気管の入り口を塞ぎ、食道に流れて胃に送られるようになっています。しかし、飲み込む機能が弱くなると、飲食物が気管に入ってしまうことがあり、これを誤嚥といい、誤嚥した物と一緒に細菌が肺に入って炎症がおこったものが誤嚥性肺炎です。死亡率が高い高齢者の肺炎のうち7割以上を占めているため、早めの対策が必要です。
誤嚥自体は、食事中にむせる・咳き込むといった症状がみられますが、発熱・咳・濃い色の痰などの肺炎の典型的な症状は、誤嚥性肺炎では出にくいのが特徴です。不顕性誤嚥といって、就寝中に気管に
入る少量の唾液や胃液などでおこる誤嚥は自覚がないため、誤嚥性肺炎を繰り返すこともあります。
食べ物を飲み込む機能が低下していないか、唾液を飲み込む動作を何回できるかでチェックする方法があります。30秒間で3回以上飲み込めれば正常、2回以下は誤嚥の危険性が高いと判断できます。予防法には、口の体操が効果的です。口を大きく開ける・口を閉じで奥歯をかみしめ口の両端に力をいれるなど、毎日行うと良いでしょう。
口の中には嫌気性菌と呼ばれる細菌が誰にでもいるのですが、この嫌気性菌が誤嚥性肺炎の原因菌となります。口の中を清潔にしていなかったり、虫歯や歯周病菌がある人ほど嫌気性菌の数は多いため、若い人でも誤嚥性肺炎を起こすことがあります。就寝前の歯磨きをしない・早食い・食べたらすぐ寝る等の習慣のある方は、注意が必要です。むし歯や歯周病の治療だけでなく、年1回は歯科健診を受診し、歯の健康を保つよう心がけてください。
加齢と高血圧(2023年12月)
 血圧とは動脈内の血液の圧力のことです。心臓が収縮して血液を全身に送り出す収縮期血圧が140mmHg以上、心臓が拡張して血液が戻ってくる時の拡張期血圧が90mmHg以上を高血圧といいます。
血圧とは動脈内の血液の圧力のことです。心臓が収縮して血液を全身に送り出す収縮期血圧が140mmHg以上、心臓が拡張して血液が戻ってくる時の拡張期血圧が90mmHg以上を高血圧といいます。
加齢により血管の弾力が低下し血流が悪くなると、心臓はより強い力で血液を送り出す必要があるため収縮期血圧が高くなってきます。高齢者の約3分の2は血圧が高いといわれています。血圧が高いまま放っておくと、心臓に負担がかかり心臓の筋肉が厚くなる心肥大や、脳の血管が破けてしまう脳出血の他、腎障害や網膜症など全身に影響をきたします。
血圧は朝から日中が高く夜間に低くなりますが、高齢者はこのリズムがくるい夜間高血圧や早朝高血圧があらわれることが多く、この状態を知らずに放置しておくと脳卒中や心臓病のリスクが高まります。
血圧の一日のリズムを保つためには、睡眠・運動・低塩などを習慣化するとともに、冬場の入浴やトイレなどの急激な温度変化にも気をつけましょう。起床時は急激に起き上がらずストレッチなどをしてゆっくりと身体の活動準備をすることを心がけてください。野菜・果物・魚をバランスよく食べ、塩分の排出に役立つカリウムやカルシウムを積極的に摂りましょう。脱水も血圧が高い要因になるため、喉が渇いていなくてもこまめに水分を摂ることも大切です。ご自宅で血圧測定をし、収縮期血圧135mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上が1週間程度続く場合は、かかりつけ医または循環器科を受診し、ご相談してください。内服が必要なタイプの方は、早めに飲み始めた方が血圧の安定も早く、動脈硬化の促進予防につながります。
脂肪肝は肝硬変に進行します(2023年11月)

食事で摂った脂質や糖質は中性脂肪に変化し肝臓に蓄積されます。肝細胞の5%以上に脂肪が蓄積された状態を脂肪肝といいます。自覚症状がなく放置しがちですが、進行すると肝臓は繊維化し、肝硬変、さらには肝がんへと進行することがあります。
予防と改善には、食べすぎや飲みすぎを控えることが基本です。特に、脂っこいものを減らすだけでなく、糖質を多く含む果物やご飯・パン・麺類などの主食の摂りすぎに気を付けてください。野菜・海藻・きのこ類などの食物繊維は糖質の吸収を穏やかにし、肝臓への負担を
減らします。緑黄色野菜は、ビタミンやミネラルの摂取にもなり、身体の調子を整える効果もあるため毎食たっぷり摂りましょう。ストレスや喫煙、紫外線などから発生する活性酸素を浴び続けると、脂肪肝の発症に影響します。カテキンは活性酸素を消去する役割があるため、緑茶を飲む習慣を持ちましょう。
筋肉は第2の肝臓といわれていて、筋肉が増えると代謝が良くなります。軽く汗をかく程度の有酸素運動にプラスして、スクワットやももあげ・片足立ちなどの筋トレを1日5から10回とりいれる等、毎日身体を動かすことが大切です。腰や膝が痛い場合は、椅子に座って出来る上半身の運動を、無理のない範囲でおこなうよう心がけてください。
確定診断には超音波や肝生検等の検査が必要になりますが、血液検査の肝機能値で脂肪肝の傾向はわかります。ALT(GOT)値が30u/Lを超えたらかかりつけ医に相談する目安となります。少し値が高くなった時点で生活を見直すことで、発症予防・重症化予防につながるため、年1回は必ず健診を受診して確認しましょう。
インフルエンザを予防しよう(2023年10月)
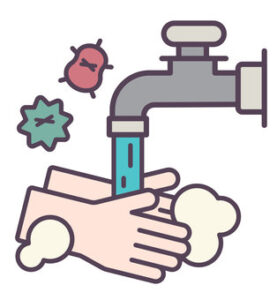 インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性ウイルス性疾患です。季節問わず乾燥や低温の場所で長く生存できるウイルスで、空気中では湿度が50%以上あると8時間ほどの寿命があり、乾燥状態では1日以上生存します。例年11月頃から増え始め、1月頃に流行がピークに達し4月過ぎに収束しますが、猛暑による涼しい室内で過ごすことが多かったことや、海外からの渡航制限がなくなったことにより、今年は8~9月の都内感染者数が多い状況でした。
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性ウイルス性疾患です。季節問わず乾燥や低温の場所で長く生存できるウイルスで、空気中では湿度が50%以上あると8時間ほどの寿命があり、乾燥状態では1日以上生存します。例年11月頃から増え始め、1月頃に流行がピークに達し4月過ぎに収束しますが、猛暑による涼しい室内で過ごすことが多かったことや、海外からの渡航制限がなくなったことにより、今年は8~9月の都内感染者数が多い状況でした。
喉の痛みの他、発熱・咳など、新型コロナ感染症と区別がつきにくく、また早い段階での治療が効果的ですので、早期に受診し診断してもらいましょう。自己判断で抗ウイルス薬などを飲んでしまうと、薬剤耐性ウイルスを誘導することもありますので、必ず医師の判断のもと治療をしてください。発症してから3~7日間はウイルスを排出し、熱が下がっても2日間は感染させる可能性があります。学校保健法では出席停止期間を「発症から5日後、かつ解熱から2日後まで」と定めています。職場復帰できるタイミングについては、会社で特に定められていなければ、発症から5日及び解熱から2日間経過してからと考えたほうが良いでしょう。
手あらいとうがいは基本です。日頃から免疫力を高める生活習慣を身につけて、感染しないよう心がけてください。栄養のある食事で体力の保持を、そしてウォーキングなどの有酸素運動で心肺機能を高めておきましょう。取っ手や机などの日頃使用する物は、アルコール度60%以上のウエットティシュ等で拭き取る事も有効です。ウイルスを吸い込むことを防ぐマスクの着用は感染防止に役立ちます。発症と重症化予防には、予防接種を受けておくと安心ですので、かかりつけ医にご相談ください。
大人の喘息(2023年9月)
 気管支喘息は、空気の通り道である気道(気管支)に炎症がおきている状態です。ちょっとした刺激でも、気管支周辺の筋肉が縮んだり、気道の粘膜がむくんだりすることで気道が狭くなり、ゼーゼーやヒューヒューといった喘鳴が起きたり、呼吸困難などの発作が生じる病気です。日本では患者数が増えており、約400万人以上が気管支喘息と診断されています。このうち、小児喘息の多くは思春期の頃には症状がよくなっていきますが、約30%は成人喘息に移行するといわれています。大人になってから初めて症状が現れる成人喘息は40~60歳代に多く、成人喘息の半数以上を占めています。
気管支喘息は、空気の通り道である気道(気管支)に炎症がおきている状態です。ちょっとした刺激でも、気管支周辺の筋肉が縮んだり、気道の粘膜がむくんだりすることで気道が狭くなり、ゼーゼーやヒューヒューといった喘鳴が起きたり、呼吸困難などの発作が生じる病気です。日本では患者数が増えており、約400万人以上が気管支喘息と診断されています。このうち、小児喘息の多くは思春期の頃には症状がよくなっていきますが、約30%は成人喘息に移行するといわれています。大人になってから初めて症状が現れる成人喘息は40~60歳代に多く、成人喘息の半数以上を占めています。
アトピー性素因などの遺伝的要素の他、ハウスダストやダニなどのアレルギー、ほこりやたばこなどによる気道の刺激、ストレスなどが原因となり発症するため、誰にでも起こりうる病気です。
治療は、発作が起きた時の薬や日頃から長期に使う薬など、症状や体調によって異なるため、かかりつけ医や呼吸器専門医にご相談してください。予防及び治療に際して重要なのは、発作を誘発する物質や状況を少なくすること、薬を医師の指示通り適切に使うこと、重い発作が起きた時は速やかに受診することの3点です。
疲労がたまると風邪をひきやすくなったり、アレルゲンに対してより敏感になるため、質のよい睡眠をとることは大切です。ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動は、心肺機能が高まり基礎体力の向上につながります。天気や気圧などの影響も受けやすいため、気温の変化に合わせて服装を調節したり、室内の保温に注意しましょう。たばこの煙は気道の刺激になるだけでなく、喘息のもとである炎症を悪化させます。また、喘息の治療薬である吸入ステロイド薬の効きも悪くなりますので、禁煙は基本です。
