こんにちは保健師です!
加齢と難聴(2025年4月)
 加齢以外に特別な原因がなく、音を感知する耳の中の細胞減少により引き起こされる聴力低下を、老人性難聴または加齢性難聴と呼びます。聴力低下には左右差がなく、特に高い音から聞こえにくくなるのが特徴です。60歳代後半頃から症状が現れる人が多く、80歳になると男性では8割以上、女性では7割以上の人にみられます。
加齢によって感覚細胞や神経細胞が減少する明確なメカニズムは解明されていませんが、遺伝、高血圧症・糖尿病・動脈硬化などの健康要因、音響曝露(大きな音にさらされること)や喫煙などの生活習慣が関与していると考えられています。
具体的な症状としては、高い音域の成分を含む“さ行”と“か行”が聞き取りにくくなることが多く、雑音の中での音の聞き分けも苦手になります。一般的に年齢を重ねると、会話に必要なことばを聞き取って理解する能力も低下していくため、音そのものの聞こえの低下と、ことばを正確に聞き取る力の低下が相まって会話が困難になることがあります。また、慢性的な耳鳴りを自覚する人も多いようです。
生理的な変化によるため誰にでも起こりうることで、完全に予防する方法は今のところありませんが、加齢以外の原因を避けて発症や進行を遅らせることは可能です。大音量のテレビの視聴やヘッドフォンで音楽を聴く等は避け、耳に優しい生活を心がけましょう。動脈硬化は発症リスクを高めるため、栄養・運動・睡眠・禁煙などの健康的な生活習慣が大切です。耳のマッサージで血行を良くすると耳鳴りが改善されることがあります。聞こえにくいと感じたら早めに耳鼻科で診てもらうとともに、定期的な聴力検査も大切です。
加齢以外に特別な原因がなく、音を感知する耳の中の細胞減少により引き起こされる聴力低下を、老人性難聴または加齢性難聴と呼びます。聴力低下には左右差がなく、特に高い音から聞こえにくくなるのが特徴です。60歳代後半頃から症状が現れる人が多く、80歳になると男性では8割以上、女性では7割以上の人にみられます。
加齢によって感覚細胞や神経細胞が減少する明確なメカニズムは解明されていませんが、遺伝、高血圧症・糖尿病・動脈硬化などの健康要因、音響曝露(大きな音にさらされること)や喫煙などの生活習慣が関与していると考えられています。
具体的な症状としては、高い音域の成分を含む“さ行”と“か行”が聞き取りにくくなることが多く、雑音の中での音の聞き分けも苦手になります。一般的に年齢を重ねると、会話に必要なことばを聞き取って理解する能力も低下していくため、音そのものの聞こえの低下と、ことばを正確に聞き取る力の低下が相まって会話が困難になることがあります。また、慢性的な耳鳴りを自覚する人も多いようです。
生理的な変化によるため誰にでも起こりうることで、完全に予防する方法は今のところありませんが、加齢以外の原因を避けて発症や進行を遅らせることは可能です。大音量のテレビの視聴やヘッドフォンで音楽を聴く等は避け、耳に優しい生活を心がけましょう。動脈硬化は発症リスクを高めるため、栄養・運動・睡眠・禁煙などの健康的な生活習慣が大切です。耳のマッサージで血行を良くすると耳鳴りが改善されることがあります。聞こえにくいと感じたら早めに耳鼻科で診てもらうとともに、定期的な聴力検査も大切です。
虚血性心疾患の原因と対策(2025年3月)
 心臓は、心臓の筋肉(心筋)が1日に約10万回も収縮と拡張を繰り返して、全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。心筋に酸素や栄養素を含む血液を送り込んでいるのが心臓の周りを通っている冠動脈という血管です。この冠動脈が狭くなったり(狭心症)、閉塞して心筋に血液がいかなくなったりすること(心筋梗塞)を心筋虚血といいます。虚血性心疾患における一番の危険因子は動脈硬化で、高血圧症・糖尿病・脂質異常症・喫煙・肥満等によって発症しやすくなります。
心臓は、心臓の筋肉(心筋)が1日に約10万回も収縮と拡張を繰り返して、全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。心筋に酸素や栄養素を含む血液を送り込んでいるのが心臓の周りを通っている冠動脈という血管です。この冠動脈が狭くなったり(狭心症)、閉塞して心筋に血液がいかなくなったりすること(心筋梗塞)を心筋虚血といいます。虚血性心疾患における一番の危険因子は動脈硬化で、高血圧症・糖尿病・脂質異常症・喫煙・肥満等によって発症しやすくなります。
狭心症と心筋梗塞の違いは、締め付けられるような痛みが15分以上続くかどうかがキーとなり、必ずしも痛みは心臓ではなく、肩や首、奥歯や喉の痛みを感じる場合もあります。心筋虚血により心筋の収縮力が弱まり、動くと息切れがしたり浮腫などの症状がでたり(虚血性心不全)、致命的な不整脈(心室細動)を引き起こすこともあります。
一度つまってしまった血管は元には戻りませんが、運動することでつまった血管の代わりとなる新しい血管がでてきます。ウォーキングやストレッチなどの手軽にどこでもできる運動から始めてみませんか。排便時にいきみすぎると血圧を上昇させ心臓に負担をかけるため、食物繊維の多い野菜の摂取やお腹のマッサージなどで日ごろから便秘予防に努めましょう。入浴は、熱いお湯は血圧や脈拍が上昇し心臓に負担をかけるため、39から40度のぬるま湯で長湯はしないよう心掛けてください。
健診を受診し血圧や血糖値等を確認するとともに、喫煙や肥満などは避けられるよう生活を見直すことが大切です。ちょっとした体調の変化をすぐに相談できる、かかりつけ医をもっておくと安心です。
立ち仕事と下肢静脈瘤(2025年2月)
 血管が拡張し、下肢静脈瘤の発症リスクが高くなります。1日10時間以上1か所に立ってあまり動かない立ち仕事の方に多く、肥満や便秘などがあるとさらに悪化させることがあります。下肢静脈瘤は、血管(静脈)がコブのようにふくらんだ状態で、クネクネ・ボコボコして目立ったり、クモの巣のように細い血管が透け長時間、脚を動かさない状態が日常的になっていると、重力で下肢に血液が溜まりて見えて目立ったりします。良性の病気ですが、自然に改善せずに時間の経過とともに徐々に悪化し、足のだるさやむくみなどの症状が慢性的におこると生活の質を低下させます。まれに湿疹や潰瘍ができ重症になることもあります。
血管が拡張し、下肢静脈瘤の発症リスクが高くなります。1日10時間以上1か所に立ってあまり動かない立ち仕事の方に多く、肥満や便秘などがあるとさらに悪化させることがあります。下肢静脈瘤は、血管(静脈)がコブのようにふくらんだ状態で、クネクネ・ボコボコして目立ったり、クモの巣のように細い血管が透け長時間、脚を動かさない状態が日常的になっていると、重力で下肢に血液が溜まりて見えて目立ったりします。良性の病気ですが、自然に改善せずに時間の経過とともに徐々に悪化し、足のだるさやむくみなどの症状が慢性的におこると生活の質を低下させます。まれに湿疹や潰瘍ができ重症になることもあります。
むくみ(浮腫)は、皮下脂肪に余分な水分がたまった状態です。靴下の跡が残ったり、すねを指で5秒ほど強く押すとへこんだまま戻らなくなるため、ご自身でも早期に確認できます。かかとの上げ下げを繰り返すなど、ふくらはぎの筋肉のストレッチや、入浴中に脚の下から上に軽くさするようなマッサージを日ごろから行っていると、予防につながります。
症状が強いと外科的治療が必要になる場合もありますが、医療用の弾性ストッキングの着用等で症状の軽減や再発予防につながることが多いです。診療科は、血管外科が一般的で、心臓血管外科・一般外科・皮膚科・形成外科などでも診てもらえます。下肢静脈瘤を専門にするクリニックもあるため、まずは、かかりつけ医に早めにご相談ください。
寒い季節の痛風対策(2025年1月)
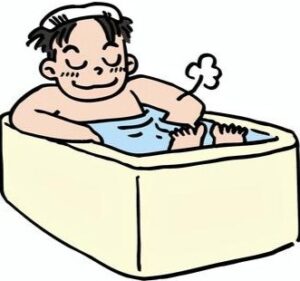
風が吹くだけで痛みを感じるため痛風と名付けられました。尿酸の血中濃度が高く結晶が関節に蓄積し、炎症発作が起きる病気です。国内の患者数は100万人を超え、予備群の高尿酸血症者は1,000万人とも言われています。腎臓で除去される尿酸が少なすぎるか、身体内でつくられる尿酸が多いことでおこります。食品に含まれているプリン体は代謝されると尿酸になりますが、血液中に含まれる尿酸の8割程度はプリン体摂取とは関係なく新陳代謝で生成されるため、レバーや干物などのプリン体含有量が多い食べ物を避けても尿酸値が上昇することが多くあります。
夏は汗をかくため身体内の水分が失われ尿量が減ることで尿酸が排出されにくくなり発症することが多いのですが、冬場の原因は、寒さによる血行不良や運動不足などによって尿酸が結晶をつくりやすくなることがあげられます。よって、手足を温めることが痛風発作の予防につながります。入浴はシャワーですませずに、38から40度のぬるめのお風呂に15分ほど浸かるのも効果的です。内臓脂肪の蓄積は尿酸産生を亢進させたり、インスリン抵抗性(ブドウ糖をエネルギーに変換できない状態)により尿酸の再吸収が促進されるため、暴飲暴食は避け適正体重を保ちましょう。尿酸値の高い方は、1日2リットル以上の水分摂取が必要です。喉が渇いていなくても水や麦茶などのカロリーやカフェインの含まれない飲み物でのこまめな水分補給が大切です。ストレスは交感神経の働きが強まり代謝が活発化されるため尿酸が促進されます。ストレスの解消と血流を良くする、ウォーキングなどの有酸素運動がお勧めです。痛風発作を予防して、寒い冬を快適に過ごしましょう。
冷え性の予防と改善(2024年12月)
冷え性とは、手足の先や腰などが冷えやすくなる身体の状態です。冷えやすい、体温が温まりにくい体質のことで、医学的な病名ではありませんが、頭痛や肩こり・便秘や下痢・不眠やうつなどを伴うこともあり、悪化すると内臓や免疫機能の低下から重篤な症状をきたす場合もあるため、注意が必要です。
主な原因としては、筋肉不足・自律神経の乱れ・基礎代謝の低下等があり、バランスのとれた食事・定期的な運動・質の良い睡眠が大切となります。腰から下の下半身、お尻やふくらはぎの冷えるタイプの下半身型は、筋肉のコリによる血行不良が考えられます。手先や足先の冷えが強い四肢末端型は、食事量が少なかったり運動不足によるものが多いです。手足は温かいものの下腹部や二の腕に冷えを感じたり、下痢などの症状が続く内臓型は、交感神経の働きが弱いことでおこりやすいと言われています。基礎代謝の低下でおこる全身型は、ストレスや生活習慣の悪化の影響が考えられます。
筋肉や血液の元となる、たんぱく質(鶏ささみや豚ロース等の肉・マグロやかつお等の魚・たまご・納豆などの豆類)や鉄分(レバー・あさりやしじみ等)を意識して摂りましょう。身体を温める生姜・れんこんやゴボウ等の根菜類もお勧めです。ストレッチで血行を良くし、ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動と、スクワットなどの筋トレを組み合わせておこなうと効果的です。入浴は、38~40度くらいのぬるめのお湯にゆっくりつかることで、自律神経の働きが良くなります。
生活習慣を見直しても冷えが改善しない場合は、甲状腺や末梢動脈疾患などの疾病による場合もありますので、かかりつけ医にご相談ください。
過敏性腸症候群(IBS:irritable bowel syndrome)(2024年11月)
IBSは、特に消化器疾患がないにも関わらず、腹痛と便秘または下痢を慢性的に繰り返す病気です。日本における有病率は10~20%で、7人に1人が罹る、特に思春期の女性や40歳代の男性に多いといわれています。大腸がんや炎症性腸疾患などの他の病気でも同じような症状がおこりますが、IBSでは体重減少・血便・発熱などは起こりません。
主な原因は、ストレス・不安・抑うつ・恐怖などの心理的要因や自律神経失調とされています。脳腸相関と言い、脳と腸は常に情報交換をしあい互いに影響を及ぼしあう関係にあります。ストレスがかかると脳からの遠心性神経により消化管運動異常などがおこり、また、内臓知覚過敏などによる痛みは求心性神経により脳に伝わり、不安・うつなど心理状態に陥りやすくなります。
予防や治療には、規則正しい生活・睡眠時間の確保・ストレスをためない、そしてリセットできる環境が大切です。刺激物の食事は出来るだけ避け、寝る直前に食べなければいけない場合は、雑炊やうどん・豆腐や鶏肉・りんごなどの消化の良い食べ物がおすすめです。お腹の調子が悪くなる食べ物が特定されている場合はそれを避けるだけで症状が良くなることもあります。趣味や楽しみなど、ストレス解消法はいくつかもっておくとより効果的です。
症状を繰り返す場合は、消化器科を受診し確定診断をうけることが大切です。整腸作用のある薬や痛み止めの他、抗うつ剤・抗不安薬、漢方薬などや、必要な方には心理療法(カウンセリング)の処方もされるため、早めにご相談してください。
コレステロールとの付き合い方(2024年10月)
 LDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪等は、たんぱく質に結合し血液中に溶けてエネルギー源として使用されています。LDLコレステロールは、ホルモン産生や細胞膜の形成などの大切な役割がありますが、多すぎると血管壁に蓄積して炎症反応を起こし、血管を傷つけ動脈硬化を促進してしまいます。HDLコレステロールは、蓄積したコレステロールを除去し抗酸化作用や血栓予防作用があるため、動脈硬化の予防につながります。
LDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪等は、たんぱく質に結合し血液中に溶けてエネルギー源として使用されています。LDLコレステロールは、ホルモン産生や細胞膜の形成などの大切な役割がありますが、多すぎると血管壁に蓄積して炎症反応を起こし、血管を傷つけ動脈硬化を促進してしまいます。HDLコレステロールは、蓄積したコレステロールを除去し抗酸化作用や血栓予防作用があるため、動脈硬化の予防につながります。
コレステロールを摂りすぎないことも大切ですが、ポイントは排出量を増やすことで、ねばねばヌルヌルした水溶性食物繊維を含む食品(納豆・オクラ・わかめ・きのこ・やまいもなど)をよく噛んで食べましょう。抗酸化物質(ビタミンA・C・Eとポリフェノール)は、LDL増加の予防になります。ビタミンAとEは、緑黄色野菜・魚や鶏肉・レバーに、ビタミンCは、じゃがいもやさつまいも・かんきつ類・キウイフルーツ・いちご・柿などに多く含まれます。ただし、ビタミンCは一度にたくさん摂ってもすぐに尿中に排泄されるため、毎食で野菜をたっぷりとる方が効果的です。魚に含まれるオメガ3脂肪酸のEPAやDHAは抗炎症作用があります。特に、まぐろ・さんま・さば・いわし・あじ・かつお・ぶりなどに含まれます。熱に弱く酸化しやすいため、調理方法としては生で食べるお刺身が最適です。
ややきついと感じられる程度の中強度以上の運動は、高コレステロールの予防と改善になります。特に、身体内の糖質や脂質をつかって筋肉を動かすウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動お勧めです。短い時間を数回に分けてもかまわないので、1日合計で30分程度行うと良いでしょう。
10月10日は目の愛護デー(2024年9月)
目の愛護デーは、目の健康や大切さに関する活動や報告が行われる日です。人は外界からの情報の80%以上を目から取り入れています。40歳を過ぎると体力が衰えるのと同じように目も衰えてきます。加齢による視機能の低下をアイフレイルといいます。最初はたまに見えにくさを自覚する程度で、進行すると、目が疲れやすい・まぶしく感じる・まっすぐの線が波打って見える・信号や道路標識を見落としそうになった等、日常生活に不安を感じるようになります。
早めに適切な治療や対処をおこなうことで進行を抑えることができます。放置して重度の視機能障害に至ると回復は難しく、視機能障害を持つ人の割合は年齢とともに増加し、2030年には200万人に達すると推計されています。
栄養や睡眠をしっかり摂ることが基本です。適度な運動で血流を良くすること、直射日光を浴びすぎないよう気を付けることも大切です。喫煙は、健康な細胞を壊す活性酸素を過剰に作り出し、加齢性の目の疾患を増悪させるため、禁煙は必須です。パソコン作業や車の運転などでは、1時間に1回、10分程度は目を休ませるようにしましょう。テレビなどのモニター画面は、見上げるよりも少し下に設定すると目が疲れにくくなります。
目の疲れが解消せず、目や身体に症状がでてくるような場合を眼精疲労といいますが、それは緑内障や白内障などの目の病気や、糖尿病や高血圧、虫歯、耳や鼻の病気など、全身の病気が影響していることもあります。加齢のせいだと判断せず、症状がある場合は早期に受診し、原因を早めに知るようにしてください。
手足口病(2024年8月)
 手足口病は、手のひらや口の中などに水疱性の発疹ができる、コクサッキーウイルスやエンテロウイルス等による急性ウイルス感染症です。主な感染経路は、くしゃみや咳による飛沫感染ですが、感染者の便に含まれたウイルスが口に入ることでうつる糞口感染や、ドアノブやつり革などを触ることでうつる接触感染もあります。
手足口病は、手のひらや口の中などに水疱性の発疹ができる、コクサッキーウイルスやエンテロウイルス等による急性ウイルス感染症です。主な感染経路は、くしゃみや咳による飛沫感染ですが、感染者の便に含まれたウイルスが口に入ることでうつる糞口感染や、ドアノブやつり革などを触ることでうつる接触感染もあります。
5歳以下の乳幼児を中心に流行しますが、大人も感染することがあります。発疹の強い痛み・全身倦怠感・関節痛・筋肉痛・高熱など、大人の方が症状が重くでることがあるのが特徴です。また、ウイルスがいくつもあるため、一度罹っても何度も罹る場合もあります。今年は夏に大流行していますが、秋から冬にかけてもみられる感染症です。
感染後の潜伏期間は3~5日ですが、ウイルス排出は1~2週間、まれに数か月にわたることがあります。特別な治療法はなく、対症療法となりますが、まれに髄膜炎や心筋炎などの重篤な合併症を伴うことがあるため、体調不良を感じたら早めに受診しましょう。
手洗い・うがいの習慣化と、日ごろから免疫力を高めておくことが大切です。特に、
トイレやおむつ替えの後などは、ハンドソープと流水で20秒以上洗いましょう。睡眠不足は免疫力低下につながります。休日の寝だめ等で調整するのではなく、睡眠時間を毎日同じくらい確保してください。飲酒は睡眠の質を悪くするため、寝酒は控え、飲みすぎないようにしましょう。日焼けは体力とともに免疫力を下げることもあるため、長時間の日光浴は避け、長時間の屋外での作業には気を付けましょう。暴飲・暴食は胃や腸に負担をかけます。腸が疲れると免疫力も下がるため、腸内の善玉菌を増やす納豆やヨーグルトなどの発酵食品はお勧めです。
ばね指(指の腱鞘炎)(2024年7月)
手の指には、屈筋腱と靭帯性腱鞘という組織があり、屈筋腱が靭帯性腱鞘の中を行き来することで、滑らかに指を曲げたり伸ばしたりすることができます。炎症が起こり腱が腫れて厚くなったりすると、擦れて痛みを感じるようになるだけでなく、引っかかりが生じ、ばね現象が起こります。特に、親指・中指・薬指での発症率が高くなります。
パソコンのキーボードやマウスの操作・ゴルフやテニスなどの手を使うスポーツ・強い力で包丁を取り扱う料理人の方など、日常で手や指をよく使っている人は、腱に大きな負担がかかり炎症が起こりやすくなります。また、女性ホルモンのバランスの崩れやすい妊娠中や産後、更年期の女性や、糖尿病や関節リウマチなどを患っている方は、血行不良によって腱鞘が狭窄しやすく発症のリスクが高まります。
炎症を和らげるために安静にすることは重要ですが、固定をすると関節が拘縮する可能性があるため、熱感のある時は患部を冷やし、手指のこわばりがある時は温めることで血行が改善し痛みが和らぎます。適度な運動で柔軟性を保つことが大切なため、指を伸ばしたりしっかり握ったりするグーパー運動であるセルフストレッチを普段からおこなっておくと良いでしょう。指を伸ばすときは指の間をしっかり広げ、指が反るくらい行い、握る時は2秒程度ギュッとしっかり握ると効果的です。
治療には、安静の他、ステロイド注射や、再発を繰り返す場合は手術療法がおこなわれることもあります。また、完治までに時間がかかる場合も多いため、指の曲げ伸ばしが滑らかでない・指のこわばり・動かしにくさ・曲がったまま伸ばせない等の症状がある場合は、早めにかかりつけ医や整形外科にご相談してください。
